育児という言葉の守備範囲

Twitterを見ると今日も色んなところで奥様が育児参加しない旦那への怒りを呟き、
また、いわゆるイクメンアカウントが同僚や上司の育児参加への意識の低さ悪く言いっている。
2つとも大変いいねの数が多く、日本男児の育児参加率の低さが伺える。
このような争いは早く無くなれば良いのにと思うばかりだ。
例えば(ちょっとボカすが)イクメンアカウントは
「同僚が母の日くらい嫁を休ませないとみたいな事を言って頷き合っていたので『え?それっていつも嫁が大変だと分かりつつも何もせず母の日だけ特別扱いしてるって事?性格悪くない?』みたいな事を言ったらその場が凍り付いた。」というようなツイートをしていた。
いやちょっと待ってくれ。
そんな人が現実に存在したらそいつはかなりコミュニケーション能力が低い。よく会社員が務まるなぁというレベルだ。
正論で世を斬る事に酔っているのか攻撃力が強過ぎる。
現実には
同僚A「母の日くらい嫁を休ませないと。」
同僚B「偉いね。俺たちももっと普段から育児参加しないとダメだよね。」
同僚A「確かに。」
くらいの会話であったと信じたい。
リアルに『え?それっていつも嫁が大変だと分かりつつも何もせず母の日だけ特別扱いしてるって事?性格悪くない?』なんて面と向かって言われたら1日で社内で有名人になるだろう、ひねくれ過ぎだ。
筆者はドン引きしたがコメント欄を見ると「世の中のみんなが投稿者さんみたいな人だったら良いのに!」というようなコメントが多数寄せられ盛り上がっていた。
そんな言い方する人ばっかりだったら喧嘩になるって…と思うが賛同する人が多いので筆者が少数派なのかもしれない。
因みに筆者の1日は以前まとめました。
筆者・・・40歳、妻が半年倒れた事を機に育児に覚醒。
妻・・・40歳、次男妊娠中、わずか4カ月で子宮口が開き半年寝たきりに。
長男・・・ 4歳、もっとも甘えたい時期にママが倒れたので完全にパパっ子。
次男・・・ 2歳、長男を見て育ったので同じくパパっ子。よその家庭でよく見る「ママじゃなきゃヤダ」が我が家では「パパじゃなきゃ」の状態。
では本題。
育児という言葉の守備範囲について考える。
パートナーの育児参加率が低いと考えるAさん(大体女性)、
自分は育児参加率がそこそこ高いと考えるBさん(大体男性)。
両者がなぜ争うかと言えば大抵の原因は守備範囲の認識がズレているからだろう。
数年前に「名も無き家事」という言葉が人気になった。
裏返しになっている洗濯物を元に戻す作業や、シンクの掃除などだ。
夫婦や家族で分担を決める際、「これは貴方の役割ね」と指定されない作業がそれにあたる。
洗濯物は脱ぐ時に自分が気を付ければ良いし、
シンクの掃除は洗い物⇒食器を元に戻す、という工程が終わらないと始められない作業だ。
これを育児に当てはめる
担当が明確に決まっていない作業は当然「気が付いた方だけがやっている」という状態になる。
1、お出かけ前のオムツ、着替え、濡れティッシュや水筒の準備
2、オムツの補充
3、バスタオルや下着の買い替え
4、保育園、幼稚園への提出物管理
5、そろそろ片付けなさいという係
探せばもっともっと有るだろうがとりあえず5個挙げてみた。
この5つを全て明確に「これとこれはあなたの担当ね」と決まっている家庭はおそらくごく少数だろう。
毎日やる育児や家事は目立つのでしっかり日の目を見る。
しかし不定期な物や細かすぎるものは陰に隠れている。
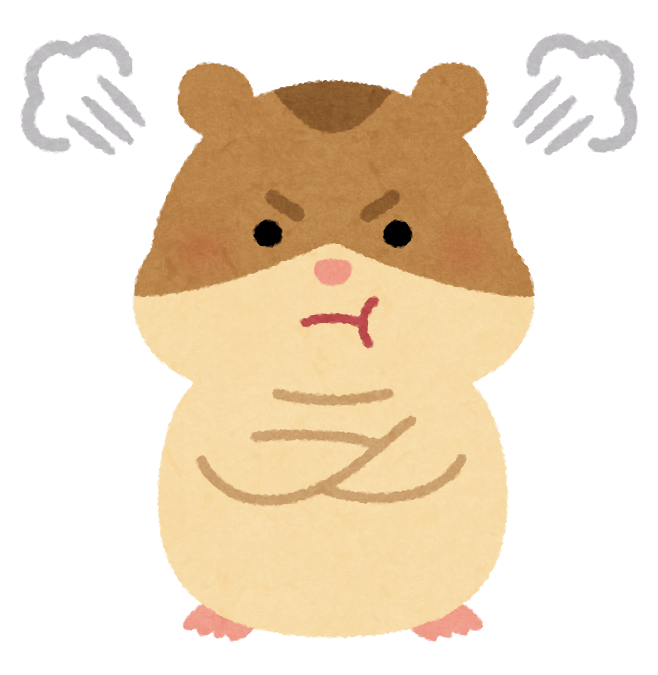
不定期な物や細かすぎるものは気が付いた方がやり続けるので、徐々に不満が溜まり「なんで自分ばかりやらなきゃいけないの」とキレる。
そしてキレられた方は「俺(私)だってやってるじゃんかよ!」とキレ返す。
認識している守備範囲が違うのだから、お前全然守れてねーよ!いや守ってるよ!という争いが起きるのは当然だ。
守ってると主張している方は決まった役割はきちんとこなしているのだから文句を言われる筋合いは無しとキレる。
しかし完全に、全て、漏れなく担当を決めるのはそもそも無理なのだ。
仕事でも「これどっちの部署がやるべき?」「なんか俺ばっかこの作業やってるけど別に担当ってわけじゃない。」という経験はおそらくみんな有る。
地道に定例会を行い育児作業リストをブラッシュアップしていくしか道は無い。
結局はおもいやり、という事に落ち着くが
自分が認識していなかった作業は普段相手がやってくれている。
それに気が付いた時はお礼を言い、役割を決める。分担したって良い。
「これ相手はこの作業の存在を認識していないな」と感じた時は優しく教えてあげる。いきなりキレず頻度や役割を決める。
名も無き育児は名前が割り振られて初めて日の目を見るのだ。
気が付いた方が貧乏くじを引くという状況が続けばパートナーからの信頼は消え失せ、何も期待されなくなるだろう。
繰り返しになるが自分がやっていない事は相手がやってくれている。
そう思ってパートナーと支え合って生きていく事が平和への第一歩だと思う。
まずはお互いの認識を合わせようという内容でした。
おしまい。